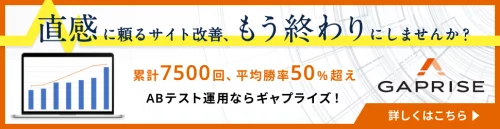ABテストとは、Webサイトを最適化するために行う検証手段の1つです。
ABテストを実施するためには、実施するタイミングを的確に見極める必要があります。
この記事では、ABテストの目的やメリット・デメリットを解説します。
また、ABテストの対象となるコンテンツやABテストを実施するステップについて紹介しますので、Webサイトの運用担当者の方は参考にしてください。
また、Google Optimizeがサポート終了し、代替のABテストツールをお探しの方は、下記レポートもご覧ください。
本レポートでは、累計7500回以上のABテスト実績をもつ専門チームによる、実際に「触って確かめた」比較結果をもとに、あなたのビジネスに適したABテストツールを選ぶことができます。
Googleが切り替え先として指定した「AB Tasty、Optimizely、VWO」を中心に比較しています。
ABテストツールをお探しの方は是非こちらからダウンロードください。目次
そもそもABテストとは
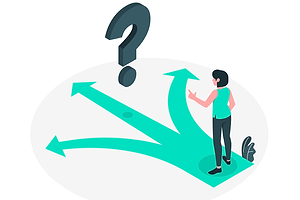
ABテストとは、バナーや広告文、Webサイトなどを最適化するために実施するテストの1つです。
複数のパターンを用意し「どちらがより良い成果を出せるのか」を検証します。
このときに用意するパターンを「Aパターン」「Bパターン」のように分類することからABテストと呼ばれています。
ABテストの目的
ABテストの目的は「CVR(コンバージョン率)」と「CTR(クリック率)向上」です。
コンバージョンとは、成約や資料請求など具体的な購買活動に繋がる割合を指します。
ABテストを実施することでパフォーマンスの高いページを見つけ、機会損失を防ぐことが目的です。
ABテストを行うことで外部要因による変化なのか、内部要因による変化なのかを明確にし、サイト改善ポイントを明確意することができます。
ABテストは少ないコストで最適なパフォーマンスを実施できます。
1からサイトを構築する必要がないため、コストを抑えながらテストを行えるのです。
ABテストを行う3つのメリット

ABテストはWebサイトを効率的に運用するためのツールです。
仮説検証をしながら最適なWebサイトの表示方法を探し出せます。
ABテストを行うメリットとして、以下の3点が挙げられます。
- 仮説検証ができる
- 小規模・低予算で実行できる
- 事前に方向性を確認できる
仮説検証ができる
ABテストを実施することで「ユーザーに刺さるプロモーションは何か?」という仮説検証を定量的に行うことができます。
Webマーケティング担当者が立てた検証が本当に正しいのか、という検証をABテストを通じて実証可能です。
例えば、LPのファーストビューを改善するとき、ABテストを通じて検証することで事前にユーザーの反応をチェックできます。
ABテストで仮説通りの成果を確認できていれば、実装の際に1つの判断材料にできるでしょう。
逆に、ABテストで仮説とは違う検証結果になれば、実装見送りの判断が可能です。
小規模・低予算で実行できる
ABテストは、小規模かつ低予算でテストが実行できます。
理由は、スピーディに改善サイクルを回せるため、時間をかけずにPDCAサイクルを回せるためです。
PDCAサイクルとは「PLAN(計画)→DO(実行)→CHECK(評価)→ACT(改善)」までの一連のサイクルを指しますが、ABテストをすることで小規模な検証ができるため、改善までに時間を要しません。
一般的に、TV広告のようなマスメディアでは効果の検証まで大規模な予算がかかります。
しかし、Web広告では数万円という低予算で実行でき、リアルタイムで結果を検証できます。
事前に方向性を確認できる
ABテストを実行することで、事前にサイトやLPの方向性を確認できます。
Webサイトをリニューアルする場合、手間やコストがかかります。
もしリニューアルに失敗した場合、これらの手間やコストが無駄になってしまうでしょう。
事前にABテストを実施することで、リニューアルリスクを防げます。
「ファーストビュー」や「フォームの内容」など、重大な要素の勝ちパターンを見つけておくことで、方向性を誤るリスクを少なくできるのです。
リニューアルには多くのコストがかかりますが、ABテストを実施することで正しい方向性が判別できる、つまり機会損失を防げるという効果があります。
ABテストのデメリットや懸念点

便利なABテストですが、使い方を間違えると誤った結論を出してしまう恐れがあります。
また、テストは継続して実施しなければならないものであり、日々変化するユーザーニーズに合わせてユーザーの動向を中止し続けなければなりません。
検証に時間がかかる
ABテストはユーザーのアクセス数が少ないと検証に時間がかかってしまいます。
ユーザーの反応をチェックしながらテストを実施するため、アクセス数が少ないと検証自体ができません。
目安としては、ユーザー数が100以下、PV数が2000以下の場合は検証までに時間がかかり、正確なデータを取得できないとされています。
また、ユーザーの反応は変化が均一とは限らないことも期間が長くなる要因です。
一定期間の検証が必要であるため、検証期間中は新しい施策ができないことにも注意しましょう。
仮説を見誤るリスクがある
ABテストで実証した仮説を見誤ってしまうリスクがあります。
ABテストは変更箇所をどこにするかによって、結果が大きく変わるものです。
そのため、仮説を誤ってしまうとサイトを間違った方向へと運営してしまうリスクがあります。
仮説を見誤らないように、しっかり熟考したうえで仮説を立てて検証する作業を行いましょう。
継続して行う必要がある
ABテストは単発的なものではなく、継続して行う必要があります。
ユーザの趣味や志向、動向は日々変化するため、継続的な実行が必要です。
常にABテストを行ってPDCAサイクルを回すことを意識しましょう。
ABテストの実施には予算と人員確保などコストがかかるものですので、社内人員や外注による社外リソースも活用することがおすすめです。
ABテストの主な対象やWebページ

ABテストはランディングページやWebページ上の広告で実施することで、ユーザーに購買などのアクションを促せるようになります。
ABテストの主な対象やWebページの事例として、具体的な効果を確認しながら見ていきましょう。
ランディングページ(LP)
ランディングページ(LP)とは検索結果や広告などを経由した訪問者が最初にアクセスするページです。
ランディングページでは「ファーストビュー」、つまり最初に見える表示の映り方や見え方が重視されます。
ファーストビューに魅力を感じてもらえないと、訪問者は早々に離脱してしまうため、ユーザーが離脱しないような魅力的なランディングページを用意しましょう。
CTA文言もコンバージョン率に大きく影響します。
CTA(Call To Action)とは「資料請求はこちら」「購入はこちら」といったように、ユーザーにアクションを促すためのものです。
CTA文言が分かりづらいものだと、訪問者は購入のためのアクションを起こしづらくなってしまいます。
CTA文言はユーザーの行動を後押しするものですので、分かりやすい表現であることを意識すると良いでしょう。
Web広告バナー
Web広告バナーはWebメディアで商品やサービスを宣伝するために設置する画像や動画などの素材を使ったものです。
画像や動画はディスプレイ広告やSNS広告で重要なポイントとなります。
例えば、GoogleやYouTube上の広告サービスでディスプレイ広告が配信できます。
画像や動画など、視覚的に訴えられる素材を使うため、ABテストによる仮説検証が効果的です。
Web広告テキスト
Web広告テキストは文字だけの広告です。
特に、見出しの文言はリスティング広告のクリック率に大きく左右します。
商品やサービスのキャッチコピーで魅力を与えられれば、クリック率が上昇するでしょう。
ABテストではWeb広告テキストで複数の見出しを検証することで、クリック率の高い見出しを選定することができます。
ABテストの実施方法4ステップ

ABテストは仮説と検証を少しずつ繰り返しながら進めていくものです。
企業を取り巻く環境や消費者の価値観は日々変化していくため、小さな検証を少しずつ繰り返すことが求められます。
ABテストを実施するには、以下の4ステップで進めていきます。
- ステップ1:目標の明確化と仮説の立証
- ステップ2:テストの実施
- ステップ3:検証結果を調査する
- ステップ4:改善を継続して行う
ステップ1:目標の明確化と仮説の立証
ABテストの最初のステップは「目標の明確化と仮説の立証」です。
バナー広告であればクリック率、ランディングページならお問い合わせや購入ページへの誘導を目指すなど、目的やゴール目標を明確にします。
目標を明確にすることで、目標に至るまでの道筋を示せます。
対象になるページが複数ある場合は、コンバージョンに近いページ、あるいは離脱率が高いページを選ぶことがおすすめです。
ABテストを実施することで定量的な比較をしやすいため、コンバージョン率や離脱率で効果を検証します。
ABテストを実施する仮説の具体例としては「ファーストビューの画像」「CTAボタンの文言」といったポイントで比較することがおすすめです。
また、メルマガのように配信時間が異なる場合は、配信時間で検証することも有効です。
ステップ2:テストの実施
ABテストで仮説を立てたら、テストを実施します。
テストの期間は短くても1週間は確保するようにしましょう。
平日と週末・休日で検証結果は異なるため、平日と休日のデータを両方参照するために1週間のテスト期間が望まれます。
1週間ではサンプル数が少ない可能性があるため、可能であれば2週間~4週間ほどの期間を確保しましょう。
1週間以上のサンプル数があれば、十分なテスト結果として立証できるでしょう。
ステップ3:検証結果を調査する
ABテストを実施する際は、必ず検証結果を調査します。
検証だけでなく、仮説そのものが正しかったかも確認しましょう。
仮説が間違っていたのか、変更した内容が訪問者に受け入れられなかったか、双方の観点でチェックする必要があります。
検証結果は必ずしも思い通りになるとは限りません。
次の検証に向けて原因を調査し、PDCAサイクルを回しながら次のABテストに繋げることが重要です。
ステップ4:改善を継続して行う
ABテストを実施した結果、改善の必要がある場合は改善を継続して行います。
ユーザーの嗜好や動向は常に変化するものであるため、テスト時には上手くいっていたとしても、実装時には動向は変わってしまうものです。
また、トレンドが移り変わった場合もユーザーの嗜好は変動します。
ABテストを繰り返し実施し、外部の小さな変化にも対応できるように小さな改善を繰り返すことが大切です。
ABテストを導入するべき3つのタイミング

自社のWebサイトが何らかの問題を抱えている場合にABテストを導入するべきです。
具体的には、以下の課題を抱えている場合に実施することが求められます。
- 離脱率が高い
- CTA動線が上手くいかない
- アクションが起こらない
離脱率が高い
離脱率が高いという課題がある場合、ABテストを導入するべきです。
「離脱率」とは、全てのページビューにおいてセッションの最後になってしまう割合を指します。
また、離脱率と似た考え方として「直帰率」があります。
直帰率とは、そのページから始まったすべてのセッションで、そのページがセッションに存在する唯一のページだった割合です。
つまり、ページを訪れて直帰してしまった割合を指します。
離脱率や直帰率が高い場合、離脱の原因をABテストで判明させる必要があります。
ABテストを通じてユーザーが離脱してしまった原因を分析しましょう。
CTA動線が上手くいかない
CTA動線が上手くいかない場合も、ABテストで原因を追及する必要があります。
例えば、ファーストビューで画像の羅列など分かりづらい情報が羅列してしまうと、ユーザーは直帰してしまうといった仮説が立てられます。
訪問者に迷いを生じるファーストビューであった場合、CTA動線は上手く機能しづらいものです。
アクションが起こらない
コンバージョンなどのアクションが思うように増えないとき、ABテストを実施する必要があります。
アクションが起こっていない場合、ABテストを実施し、ユーザーがアクションを起こさない原因を分析しましょう。
例えば、CVボタンの色、CTA誘導テキストの文言といった要素のテストを行い、仮説を立てながら変更していくことでアクションが起こることを期待できます。
1回のABテストで上手くいかない場合、何度もテストを繰り返して、最適な要素を見つけましょう。
ABテストで効率的な運用を実現しよう

ABテストはWebサイトを効率的に運用するうえで欠かせない検証です。
ABテストを実施することで、低コストで仮説検証を立てながら課題や方向性を確認できます。
ただし、ABテストは実施のタイミングや継続して行わなければ、仮説を見誤ってしまうリスクがあるため注意が必要です。
ABテストを実施するタイミングとしては、自社のWebサイトで離脱性が高い、CTA動線が上手くいかないといった課題を抱えている場合におすすめです。
ABテストを適切に実施して、自社のWebサイト運用を改善しましょう。
本メディアを運営する株式会社ギャプライズでは、WebマーケティングやWebサイト改善、Webサイト集客など、さまざまな課題や悩みに対応したビジネスを展開しています。
ABテストツールや他の比較ツールに関するご相談にも対応可能です。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。